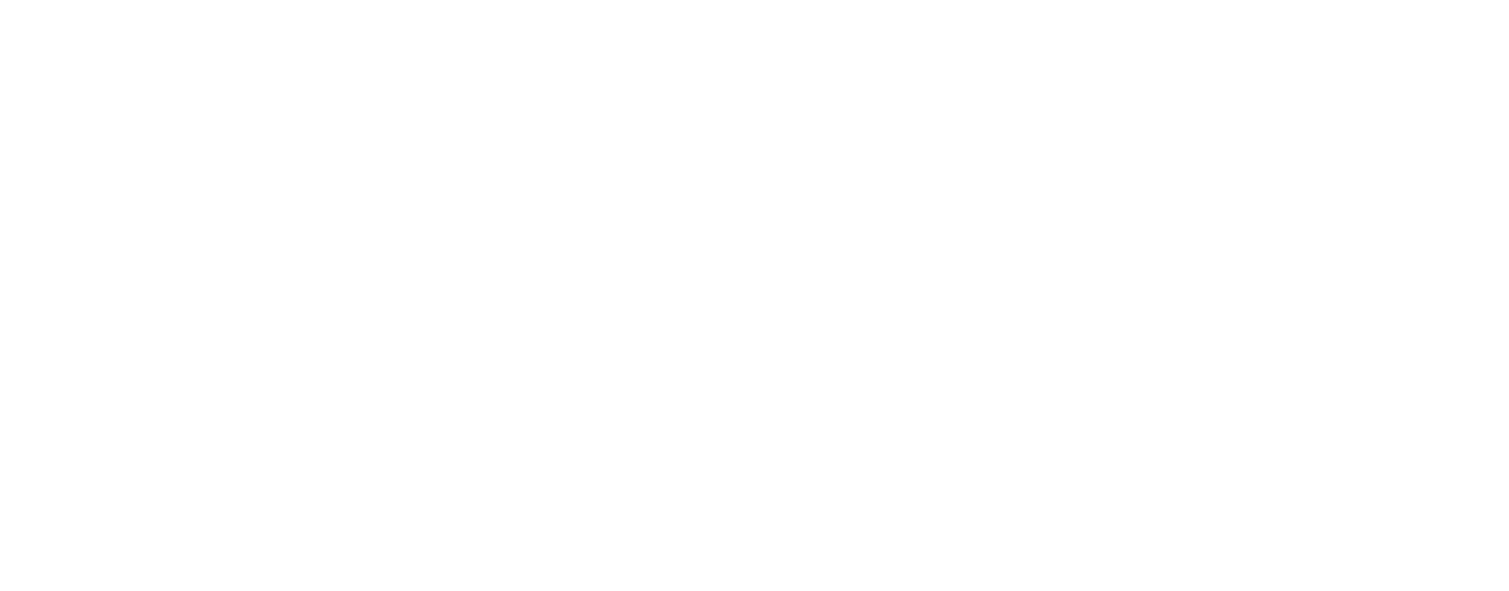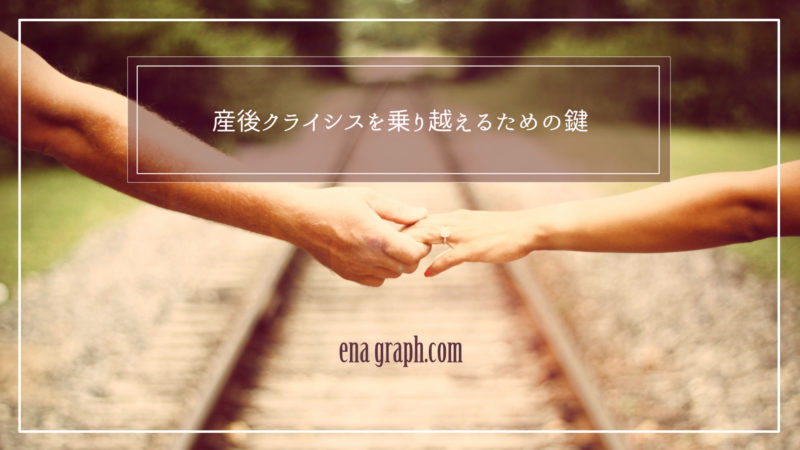産後、妻が夫への不満を募らせ、そうした妻を夫も嫌がるようになることで起こる家庭不和「産後クライシス」

もっと父親になった自覚を持って欲しい!

前はあんなじゃなかったのに…
子供ができる前はお互いを思いやり、仲睦まじい生活を送っていたのになぜ…そう感じる夫婦も多いと思います。
女性が産後、人が変わったようにピリピリしているのは、産後に分泌される”あるホルモン“が影響しているから。
産後クライシスの原因は主に、そのホルモンの影響を直に受ける妻側にあることが多いのですが、産後クライシスを回避する鍵を握っているのは、夫。
というのも、産後の妻の感情は起伏が激しく、自分でもコントロールすることが難しいからなんです。
ホルモンの影響で感情を上手くコントロールできない妻に代わって、夫婦の危機を救えるのは夫しか居ないのです。
この記事では、産後クライシスの原因と、夫婦の危機を救うための愛情が深まる行動を紹介しています。
- 今まさに産後クライシスで夫婦の危機を迎えている男性
- 産後クライシスだけは避けたいと願う、これから出産を迎える夫婦
目次
産後クライシスが起こる原因
産後クライシスの原因は夫婦によって様々ですが、特に以下の3つがよく起こる原因として考えられます。
- 妻が産後分泌されるホルモンによって自分で感情をコントロールできない
- 夫の慣れない育児に妻がイライラする
- 育児協力者の少ない環境が妻を不安にさせる
一つずつ詳しく解説していきます。
愛情ホルモンが妻の感情をコントロールする
産後クライシスは、女性が「母」になった時に訪れます。
その理由は、女性は出産の時に、大量のオキシトシン=愛情ホルモンを分泌し始めるから。
オキシトシンは、陣痛を引き起こしたり、乳腺の筋肉を収縮させて母乳を出すために分泌されるホルモン。
オキシトシンが脳に作用すると、母親は我が子への愛情が増したり、スキンシップなどの愛着行動をするようになります。
オキシトシンは出産の時以外にも、授乳によっても分泌されます。

授乳中になんとも言えない幸福感に包まれるのは、このホルモンによるものだったんだね
このオキシトシンは、我が子への愛情を増幅してくれる一方で、子供を守るために敵とみなした相手に非常に攻撃的になる働きも。
人間の世界でも、動物の世界でも、母にとって子供を守ることは最優先事項。
母にとって、愛おしい我が子を傷つけかねない存在は全て敵なんです。
なので、「夫が育児を手伝ってくれない」といった不満を妻が感じていると、攻撃対象が夫になってしまうことが。

夫の姿を見ただけでもイライラが止まらない!

そんなぁ……
私の姉もそうでしたが、一度夫を敵とみなしてしまうと、夫の嫌な部分ばかりが目について更に夫嫌いが加速してしまいます。
世界中のあらゆる調査でも、産後に夫婦の満足度が大きく下がることが分かっています。
子を守る母のホルモンがある限り、夫はよほどうまく立ち回らない限り妻を大爆発させてしまう運命なんです。

夫はつらいよ…
不完全なイクメンぶりが妻をイライラさせる
最近は子育てに積極的に参加する「イクメン」が増えてきましたよね。
でもそのイクメンにさえも、母のホルモンは時に牙を剥きます。
例えば夫が子供のお世話中に何か失敗をした時、妻は無意識のうちに夫を「子育ての邪魔をしようとする者」と認識して、強い口調で攻撃してしまうことが。

子供の世話をしても怒られてばかりだと嫌になるな…
一日中子供の世話をしている妻と、朝晩の短時間しか子供の世話をしない夫とでは、子育てスキルに大きな差が出るのは当たり前。
妻はそんな事分かっていても、つい手際の悪い夫の姿を見てイライラしてしまうものなんです。
これもオキシトシンの影響で、オキシトシンは感情を増幅させる作用があります。
オキシトシンが分泌されている状態で愛情を感じると、その気持ちは何倍にもなりますが、逆に不快だと感じると、怒りや攻撃性が何倍にも増幅してしまうんです。

(子供ができるまではどうって事ないことだったのに、どうしてこんなにも感情的になっちゃうんだろう…)
育児に積極的なイクメンは本来、妻にとってとてもありがたい存在。
それなのに「子育ての邪魔をしようとする者」なんて思われると、夫ももう子育てに関わるのが嫌になってしまうのは当たり前ですよね。
育児協力者の少ない環境が妻を不安にさせる
実家が遠かったり、地域コミュニティが薄弱なことも、妻の精神的負担を増やす要因になっています。
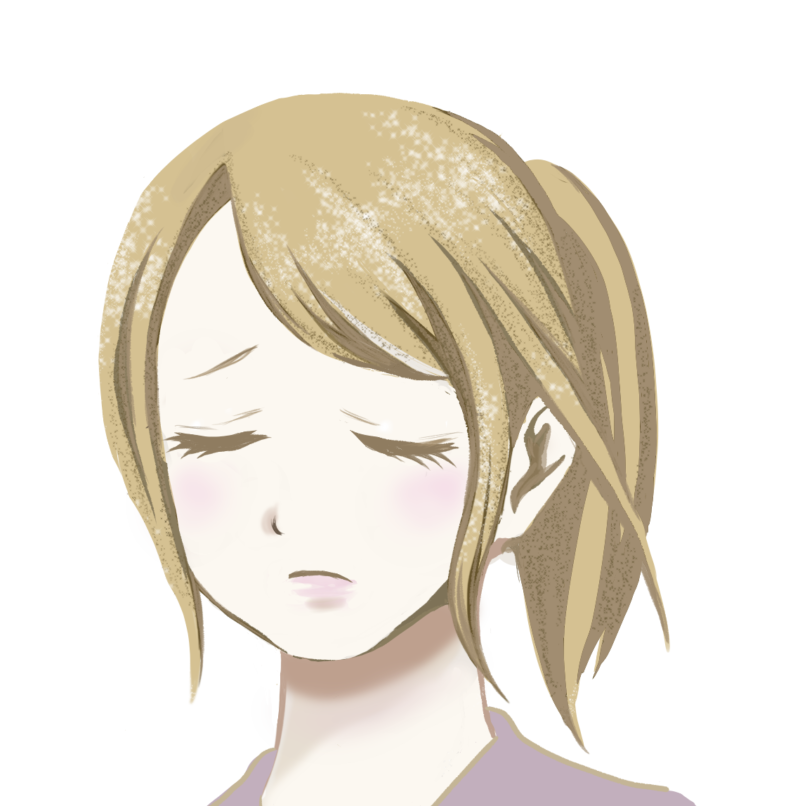
私も実家が遠いから昼間は「孤育て」なんだ…
まだ地域ぐるみで子育てをしていた時代は、子育ての不安な気持ちを聞いてくれる人が近くに居たのは新米ママにとってとても心強かったと思います。
でも現代の「孤育て」中のママは、悩みを吐き出す場がなく、子育てのモヤモヤを自分の内側にため込むしかないので精神的に病んでしまう人も。
厚生労働省の調査によると、もっとも離婚率が高いのが未子が0〜2歳の時で、産後クライシスが原因となって離婚している夫婦は年々増加しています。
産後クライシスに陥りやすい夫婦の特徴
夫婦間に以下のような特徴があったら、産後クライシスに注意!
- 夫が育児に協力的ではない
- 夫婦の会話が少ない
- 夫婦二人の時間が減った
先ほど触れたように、孤育て中のママにとって、悩みを吐き出す場は重要。
夫の仕事が忙しくて妻の悩みを聞いてあげる時間を持てていないと、妻はいつか不安とストレスで大爆発してしまいます。
産後夫婦二人の時間を取れていない場合も、子供が生まれる前のような親密な関係を維持するのは難しくなってしまいます。
産後クライシスを乗り越えるために夫がとるべき行動

オキシトシンは、愛情を深めるホルモン。
夫がこれを上手く利用することが、産後クライシスの危機を回避する鍵となります。
- 夫が育児に協力する
- 妻との会話の時間を増やす
- 妻に自由な時間を作ってあげる
夫が育児に協力する
子供が生まれたらすぐに母性スイッチが入る女性と違って、男性はなかなか父親になったという実感が湧かない!という人も多いんじゃないでしょうか?
でも、オキシトシンの分泌されない男性でも、育児体験を積み重ねることで父性スイッチをオンにすることができます。
イスラエルで行われた研究によると、父親が15分間我が子と触れ合った後の血液を調べてみたところ、愛情ホルモンであるオキシトシンが増えていることがわかっています。
夫が愛情を持って我が子と触れ合う様子を見ると、妻も夫を育児協力者と認識するようになりますよ!

でもイクメンも妻の攻撃対象になるんでしょ?
妻をイライラさせる原因の一つに「不完全なイクメン」がありましたが、一般的な自称イクメンは、妻から見るとイクメンになりきれていないことも。
妻をイライラさせないためにも、前にも増して積極的に育児をしてみてください。
でも残業があったり、連日の仕事で疲れていたり…なかなかイクメン完全体への道は険しかったりするのが現実。
そんな時は、いつもより1回多くオムツを交換するだけでも良いし、夜中子供が起きた時に、1回だけでも妻と寝かしつけを交代する…など、少しずつ育児に関わる時間を増やしてみるのはいかがでしょうか?
育児によって分泌されるオキシトシンは夫婦の愛情を深め、協力して育児に取り組んでいく意欲を助けてくれます。
夫のイクメンレベルが上がると、妻も安心して子供を任せられるはずです。
妻との会話の時間を増やす
育児のストレスを解消する方法の一つが、他愛もないおしゃべり。
育児中の女性は、子供とずっと一緒に居ることで狭い空間に閉じ込められたような閉塞感を感じています。
そんな時、友達や家族と他愛もないおしゃべりを思いっきりすることで、育児で沈んだ心が一気に浮上してきます。
でも周りに友達や家族が居なかったり、すぐに会えなかったり…。
そんな時、ベストな会話相手が夫!
会話の内容は、育児の悩みや愚痴がメインになることが多いと思いますが、話を聞いてあげるだけでも妻の気持ちはだいぶ軽くなります。
また、二人で育児をしていると共通の話題が増えて、必然的に夫婦の会話は多くなります。
私は産後、娘を寝かしつけたあとは必ず夫とゆっくりお茶を飲みながら話す時間を持つようにしていました。
話題はやっぱり育児のことが多くなるんですが、育児の苦労を夫が理解してくれていて、話を聞いてくれていることが大きな安心感につながっていました。

二人だけになると、子供ができる前のような親密な関係がまた戻ってきたような気がして親密度もアップするよ
妻に自由な時間を作ってあげる
以前、「セルフケアで産後うつを防げ!夫婦仲を守る1日3つの習慣」でも紹介しましたが、育児中の妻にとって必要なのは、自分の時間。
子供から少し離れて、心と体をチャージする「セルフケア」を行うことで、妻は育児のストレスをコントロールしやすくなります。
産後クライシスを回避する鍵は夫にありますが、妻も自分の中にたまったモヤモヤを晴らさなければ、一方的にストレスをぶつけられる夫のメンタルまでやられてしまいます。
そのためにも、短時間でも良いので妻に自由な時間を作ってあげてください。
おわりに
産後、ストレスで大爆発する妻に夫もイライラするのは当然ですが、そこで妻の気に触るような発言をしてしまうと収拾がつかなくなります。
夫が妻の育児のつらさを理解して、育児に積極的に参加することが産後クライシスを回避するためには不可欠。
育児に励む夫の姿は、妻にとってとても心強いものです。
産後の妻の急激なホルモン変化がおさまるまでは、夫にとっても妻にとっても辛い時期ですが、夫婦の時間と会話を大切にして、夫婦二人でこの大波を乗り越えていきましょう。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。